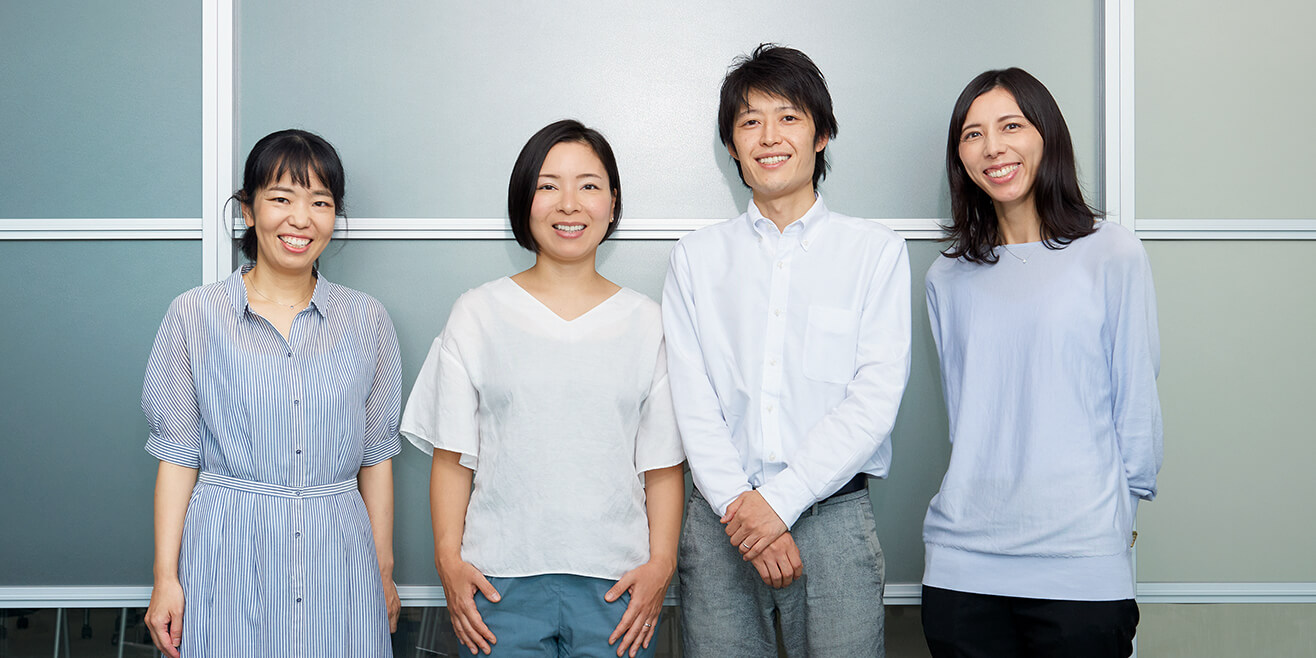- 採用情報サイトTOP
- 人を知る
- 座談会
- 社長 × 若手社員
社長 × 若手社員TALK SESSION 03

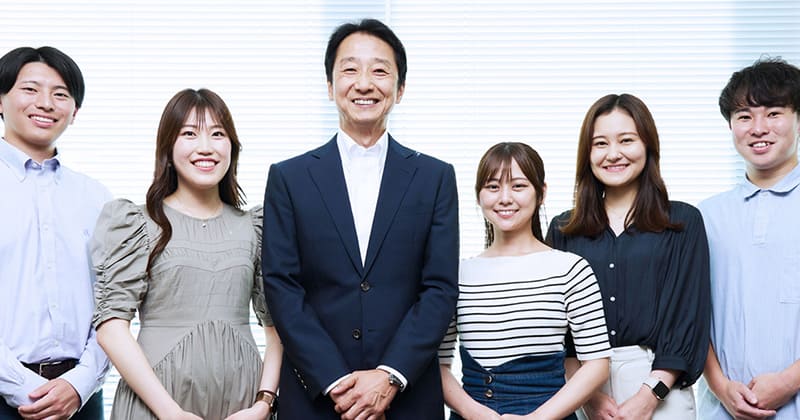
 社員A総合職
社員A総合職
輸送インフラ部
2019年入社 社員B業務職
社員B業務職
軸受国際部
2020年入社 社員C総合職
社員C総合職
特殊鋼開発部
2021年入社 社員D業務職
社員D業務職
厚板貿易部
2023年入社 社員E総合職
社員E総合職
ロジスティクス・業務プロセス部
2024年入社
三井物産スチールでは約300名が、東京の本店をはじめ、支店や海外で活躍しています。勤務地も扱う商材もさまざまな業務のなかで、社員たちは会社をどのように見ているのでしょうか? 若手社員5名が、社長の阪田に尋ねました。制度・コミュニケーション・ボトムアップ。三井物産スチールのカルチャーがわかる座談会です。
TALK SESSION三井物産スチールの
自由闊達なカルチャーの秘密

阪田:バリバリご活躍中の社員の皆さんと話せる機会ということで、楽しみにしてきました。私が営業部にいた時代に一緒に働いてくれていた方もいますね。
社員A:そうですね。阪田さんは私が初めて配属された部の隣の部長でした。席は離れていましたが、同じフロアにいらっしゃいましたよね。
社員B:私は部内のメンバーと一緒にゴルフに誘っていただいたことがありますよ。
阪田:そうでしたね。業務中のみならず、プライベートでも社員と管理職、経営側が気軽にコミュニケーションする機会が多い会社です。私はいま「車座」と称して、6-7名を1グループにして、全社員とカジュアルに対話する機会を作っており、それが社員と経営陣の直接コミュニケーションする場にもなっています。皆さんの所属組織の中でも、上司・部下の直接対話の場として、車座や1on1が積極的に行われていると思います。
社員C:既に阪田さんとの「車座」に参加された社員もいるようですね。
阪田:「車座」は全46回予定していて、いま10回を終えたところです。参加者の皆さんから多岐に亘る意見が聞けて新しい気付きもあります。皆さんにもいずれ声がかかると思います。

社員D:部署内外問わず、社員同士の交流会であっても業務上必要な情報共有を目的とするものであれば、会社で経費を出してくれる制度に驚きました。部署を越えての夕食会や、お子さんがいるメンバーはランチ会で、それぞれの担当業務について情報交換する機会があっていいですよね。
社員E:実は、私の入社後はじめての仕事は、「部門内交流会」の幹事でした! 阪田さんに開会の挨拶をお願いしに行ったこともありましたね。どうして、こんなにも社内交流を重視するようになったのでしょうか?
阪田:商社は幅広くビジネス展開して居り、皆さん忙しい毎日を過ごされています。環境の変化に対応し、顧客のニーズを察知しなければならない仕事ですが、縦と横の連携が求められます。忙しくて誰が何をやっているのか分からない、では良い仕事ができないので、風通しの良い職場作りは意識しています。「車座」は、三井物産スチールの恒例イベントになっていますが、重要な取り組みだと思います。現場が活気づいて、ボトムアップで新しいアイデアやイノベーションが生まれてくる。三井物産スチールのカルチャーの土台にもなっています。

海外駐在で感じた「三井物産スチールって何?」
社員A:管理職・経営陣とも距離が近く、立場の区別なく自分の考えや意見を伝えやすい職場ですよね。では、今の三井物産スチールにもっと必要なものは何だと思いますか?
阪田:良い質問ですね。「人の三井」と言われるように、当社はコミュニケーションが闊達で、良い人が多い、働きやすいと社内でもよく聞きます。これは、他社から転職で当社に入社された社員からもそう聞きますので、当社の1番の良さではないでしょうか。その上であえていえば、ビジネスのストイックさがもっとあっても良いと思います。人への優しさや気遣いは大切にしながら、もっとビジネスに貪欲な部分を出していってもいいのではと。
社員A:それは2025年2月までの2年間、タイに駐在していた時期にも感じました。現地にいる他商社のエネルギッシュな姿勢に刺激されることがあって。

社員B:私たちのなかで海外経験があるのは阪田社長とAさんだけですね。駐在時の話を聞きたいです。
社員A:カルチャーショックも商習慣の違いもありましたが、もちろん楽しかったですよ。私は現地でムエタイにハマり、習いはじめました(笑)。
もっとも大きい学びは、三井物産スチールを「外」から見ることができたことなんです。日本では三井物産グループは知名度も信頼感もありますが、外国の取引先にとっては「WHO IS MITSUI?」なんです。「自分たちは何者なのか」を説明しなくてはならないんですよ。
阪田:そうですね。当社の強みは何なのか、当社がどのような価値を提供しているのか、全社員で考えていきたいです。そうすることで取引先との関係は今まで以上に厚みを出せると思います。取引先のほうから「あなたの会社に頼みたい」と言われるのは商社の仕事の醍醐味と思いますが、皆さんいかがですか?

社員C:私はお客様が困ったときに自分に電話をかけてきたら「やったぞ」と思いますね(笑)。信頼関係を築けていたのだと。
阪田:そうなんです。私も入社14年目でタイに駐在しました。当時、日系の大手企業さんが、現地に工場を設立される計画を記事で見ましたが、三井物産グループと取引のない企業さんでしたので、少し他人事のように思っていました。しかし、突然その企業の方がタイのオフィスに来られ、現地で予定していた部材の調達が困難になったということで、取引実績のない当社に助けを求めに来られたのです。その企業の方の説明を聞いて、これはただ事ではない、取引の有る無しに関わらず、「何とかしなければ」と思いました。
非常に難しい案件でしたが、客先からこれだけ期待され、頼られることは、そう滅多にありません。上司の理解を得て、現地の部材サプライヤー探しに全力を注ぎ、何度も試作に立会いながら、現地での部材調達の目処をつけました。そして、その企業さんから「ありがとうございました。御社から部材を購入させて欲しい。取引させて欲しい」と言って頂いた時、必死に汗をかいて努力したことが報われたことにホッとしたと同時に、この企業さんの為に今後も精一杯やろうという気になりました。当社の努力と機能を認めてもらえた、非常に価値のある仕事でした。

若手のときにやっておくべきことは?
現場から会社を動かす「ボトムアップ組織」
社員E:私は今後の三井物産スチールの進むべき方向性をお聞きしたいです。新しく取り扱う商材を増やして規模を拡大していくのか、今までのビジネスの延長で成長させていくのか。いろいろな方向があると思いますが、どのようにお考えでしょうか?
阪田:単純に取り扱いを増やして規模を大きくすることは考えていません。今やってるビジネスも大事にしていきますが、少しずつメリハリをつけながら、我々の強みを活かした新しい取り組みにもチャレンジしたいです。結果、規模が大きくなればベターですが、規模を大きくすることだけがゴールではないと思っています。他の会社でできないような特色のある仕事を1つでも多く作りたいです。
そういう意味では、私は皆さんのような若手時代に、もっと自分の強みを伸ばしておけばよかったと思っているんですよ。語学でも資格でも何でもいい、「一芸に秀でる」こと。組織で自分が光り輝ける存在になるにはどうすべきか、見つけて欲しいと思います。
社員D:私も「一芸」を探し中で……(笑)。最近はDXに取り組みはじめました。デジタルによる業務の効率化は若手のほうが得意な分野だと思いますし。
阪田:それはいいですね。周囲の皆さんの反応はどうですか?
社員D:意見を出すと「いいね、とりあえずやってみようよ」とすぐに取り入れてくださるんですよ。後輩たちも話題に入りやすく、自由にアイデアを出しています。「この業務もDXできるかな?」と新しい視点が持てて刺激にもなりますね。先ほどの「頼られる」という話にもつながりますが、やっぱり任せてもらえると嬉しいです。
社員C:三井物産スチールは「自由闊達な組織」と言われていますが、確かに上司は細かくマネジメントするより「任せる」タイプの人が多いですよね。私も入社して半年以内で一人で担当を持たせてもらいました。「まず自分で考えて、分からないことは相談しなよ。いざという時はフォロ-するから」という感じで。
もちろんめちゃくちゃ緊張しましたけど、私には合っていると思います。入社してから1日も出社が憂鬱になったことがないんですよ。……いや、嘘っぽいけど本当ですよ(笑)! 仕事で嫌なことがあっても支えあえる仲間が近くに沢山いますから。
阪田:当社の人材育成はOJT中心ですね。まずやらせてみる、責任は上司が持つ、みたいな。以前から三井物産スチールはそのカルチャーです。社員1人1人のキャリアパスも皆さんと話し合いながら確り作っていきたいです。

社員B:阪田さんが社長になられ、理想の社長像をお聞きしたいです。
阪田:大所高所から見て強いリーダーシップを発揮することも大事ですが、私の場合、時には伴走型の社長でありたい、と思っています。メインのランナーは社員の皆さんであり、私は皆さんの横を走っているイメージ。何かあったら一緒に悩んで、一緒に考えようと。
社員B:阪田さんが営業の部長で、私の上司だったときと変わりませんね(笑)。出張からお帰りになった際、「取引先の担当者さんが君のことを褒めていたよ」と教えてくださって嬉しかったのを思い出しました。
阪田:私に限らず三井物産スチールの管理職は、そういう人が多いのではないでしょうか。当社はボトムアップ型で成長してきました。その原動力はやはり「人」です。
環境変化の著しい世の中で、若い社員の柔軟な発想、活力は今後益々大事です。総力戦で臨んでいきたいと思いますし、会社を良くしたいと熱い思いを持っている社員は、経営としても精一杯サポートしたいと考えています。
※本座談会記事は2025年6月時点のものです。

 社長メッセージ
社長メッセージ 数字で見る三井物産スチール
数字で見る三井物産スチール 三井物産グループの総合力
三井物産グループの総合力 事業の紹介
事業の紹介 鉄と鉄鋼商社
鉄と鉄鋼商社 座談会
座談会 社員紹介
社員紹介 キャリアステップ
キャリアステップ 働く環境
働く環境 ワークライフバランス
ワークライフバランス 福利厚生
福利厚生 研修制度
研修制度 求める人物像
求める人物像 選考フロー
選考フロー 募集要項
募集要項 よくある質問
よくある質問